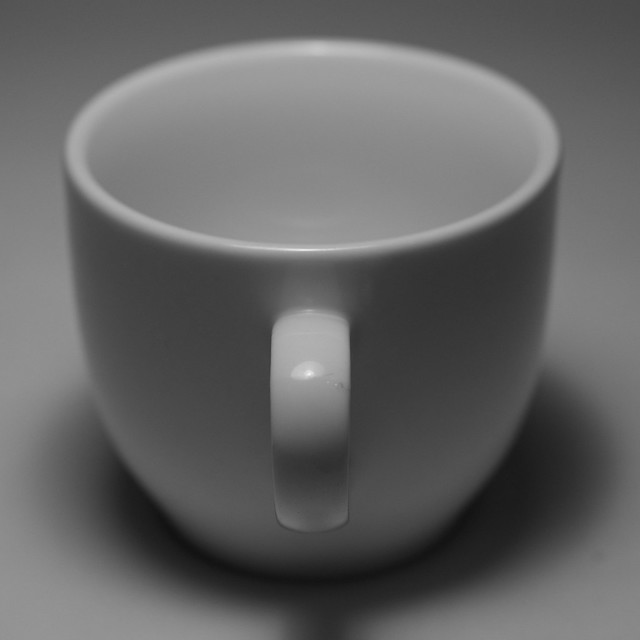地元の写真倶楽部で、千葉に在住の方の
写真展に行ってきました。
センス抜群!、世界があって、あっ!ヨシさんの写真だってわかる。
ベトナムで撮った写真のライブ感というか、肌感覚が伝わり、
地元や会社の同僚を撮った写真は、みないい顔をしている。
自宅で一般的なインクジェットプリンターで印刷したという。
紙を変えたり、セピア色で印刷したり、
あげくはコーヒーに浸したりという荒技まで。
でも、それが、独特のオリジナリティを醸しだしている。
多いに刺激を受けた写真展であった。
で、その後、せっかく、千葉まで行ったのだからと
小湊鐵道に乗って、「撮り鉄」を実践。
これもまた、久しぶりの写真倶楽部的な活動で
大いに満喫したのでした。
ほんと、今日は濃厚&充実した一日でした。
2014年9月13日土曜日
2014年9月11日木曜日
あーやんなっちゃった 泣き笑いウクレレ人生
自分にとってウクレレと言って思い浮かべるのはこの人。
高木ブーはドリフターズだし、関口和之はサザンオールスターズのベースで、
小錦は元大関。ハーブオオタやジェイクを聴いた時は驚いたけど、
大正テレビ寄席を小さい頃にいつも観ていた記憶がある自分にとって、
ウクレレと言えば牧 伸二なんである。
その生い立ちから、工場の職人時代、好きで入った芸能界とその心構え、
家族のことなどがとつとつと書かれている。
最初は声帯模写でのど自慢大会に出場し、
アガリ性で鐘はいつも一つしか鳴らなかったらしい。
そして、ウクレレとの出会いと「やんなっちゃった節」の誕生。
原曲のタフワフワイの話も出てくる。
当時のライバルは林家三平の「どうもすいません」だった。
読むと本当に芸の世界を好きなことがよくわかるし、
ステージに立つことが何より嬉しかったことが伝わってくる。
でも、芸を離れたら平凡な人間であって、
舞台が全てと思っちゃいけないと悟る話とか、
工場職人時代の専務のお嬢さんとの大恋愛の話もあったり。
ちなみに、使っていたウクレレはマーチン製。
巻末には、師匠直々のウクレレ即席講座と、
やんなっちゃった節の傑作集がついています。これは面白いすw
で、師匠もおっしゃっています
「ちょっとの時間でもいいから毎日音を出すことが大切」と。
高木ブーはドリフターズだし、関口和之はサザンオールスターズのベースで、
小錦は元大関。ハーブオオタやジェイクを聴いた時は驚いたけど、
大正テレビ寄席を小さい頃にいつも観ていた記憶がある自分にとって、
ウクレレと言えば牧 伸二なんである。
その生い立ちから、工場の職人時代、好きで入った芸能界とその心構え、
家族のことなどがとつとつと書かれている。
最初は声帯模写でのど自慢大会に出場し、
アガリ性で鐘はいつも一つしか鳴らなかったらしい。
そして、ウクレレとの出会いと「やんなっちゃった節」の誕生。
原曲のタフワフワイの話も出てくる。
当時のライバルは林家三平の「どうもすいません」だった。
読むと本当に芸の世界を好きなことがよくわかるし、
ステージに立つことが何より嬉しかったことが伝わってくる。
でも、芸を離れたら平凡な人間であって、
舞台が全てと思っちゃいけないと悟る話とか、
工場職人時代の専務のお嬢さんとの大恋愛の話もあったり。
ちなみに、使っていたウクレレはマーチン製。
巻末には、師匠直々のウクレレ即席講座と、
やんなっちゃった節の傑作集がついています。これは面白いすw
で、師匠もおっしゃっています
「ちょっとの時間でもいいから毎日音を出すことが大切」と。
2014年9月9日火曜日
ライカと味噌汁 〜 ライカが見た東京
たまたま、著者がライカで撮った写真展があり観に行ったので、
ずっと積ん読になっていた本書を読んだ。
ライカが日本に来てからどう使われてきたか、主に1960年代を書いている。
面白いのは、ライカというカメラを擬人化していることころ。
ライカがみたら東京はこんなだった、あんなだったと。
そして、ライカは冒険心をそそるカメラで、ヒマラヤ未踏峰の登頂、
大陸間無着陸飛行、人民戦線レポートと共にある感じが
日本製一眼レフにからは完全に脱落していて、
紛争地帯のデジタル一眼レフなぞは、
ハリウッドのオープンスタジオに置かれているように見えるらしい。
更にエスカレートして、ライカは写真を撮影する実用物を超えた
物質の段階になっていると。こうなってくるともはや魂とか
崇高な信仰の世界に入りそうだ。それこそ、日本人にとっての味噌汁か。
でもきっとそうなんだと思う。実際にライカを持っていないが、
観たり触ったりしたことがあるのでなんとなくイメージは湧く。
高価なカメラなので、とても手が届かないが、文中にあった、
写真ではなく精巧なイラストで作成され、
機械としての存在感が浮かび上がるというカタログを是非観てみたい。
銀座のショールームにあるかな。
ずっと積ん読になっていた本書を読んだ。
ライカが日本に来てからどう使われてきたか、主に1960年代を書いている。
面白いのは、ライカというカメラを擬人化していることころ。
ライカがみたら東京はこんなだった、あんなだったと。
そして、ライカは冒険心をそそるカメラで、ヒマラヤ未踏峰の登頂、
大陸間無着陸飛行、人民戦線レポートと共にある感じが
日本製一眼レフにからは完全に脱落していて、
紛争地帯のデジタル一眼レフなぞは、
ハリウッドのオープンスタジオに置かれているように見えるらしい。
更にエスカレートして、ライカは写真を撮影する実用物を超えた
物質の段階になっていると。こうなってくるともはや魂とか
崇高な信仰の世界に入りそうだ。それこそ、日本人にとっての味噌汁か。
でもきっとそうなんだと思う。実際にライカを持っていないが、
観たり触ったりしたことがあるのでなんとなくイメージは湧く。
高価なカメラなので、とても手が届かないが、文中にあった、
写真ではなく精巧なイラストで作成され、
機械としての存在感が浮かび上がるというカタログを是非観てみたい。
銀座のショールームにあるかな。
2014年9月7日日曜日
ぶつどり
2014年9月6日土曜日
道化の精神
太宰 治が新聞や文芸誌などに寄せたエッセイや
小説作品の中から集めた引用集とでもいうもの。
それこそ一行だけの文章とかもある。
小説ではないこういう形で太宰 治を読むのは初めてだったが、
なおのこと、厳しい文章が続けざまに入ってくる。
一つ一つがずんとくる。
例えば、短い文でも、鉈でずぶっと刺されるようなのがいくつもある。
「はじめから、空虚なくせに、にやにや笑う。「空虚のふり」」
「苦悩を売り物にするな、と知人よりの書簡あり」
「甘さを軽蔑する事くらい容易なことは無い。
そうして人は、案外、甘さの中に生きている。
他人の甘さを嘲笑しながら、自分の甘さを美徳のように考えたがる。」
全編通して思うのは、実際、君は何をしたのです?
と問われ続けている感じを受ける。
また、逆説的な表現で真意を突いてくるのも自分が太宰 治を好きなところでもある。
「子供の頃に苦労して、それがその人のために
悪い結果になったという例は聞かない。
人間は子供の時から、どうしたって悲しい思いをしなければならぬものだ。」
とかね。
最後の「如是我聞」も痛快。
某作家を徹底的に罵倒し続けている。ここまで言うか〜(笑)というくらい。
ということで、「斜陽」とこの某作家の作品も読みたくなったよ。
小説作品の中から集めた引用集とでもいうもの。
それこそ一行だけの文章とかもある。
小説ではないこういう形で太宰 治を読むのは初めてだったが、
なおのこと、厳しい文章が続けざまに入ってくる。
一つ一つがずんとくる。
例えば、短い文でも、鉈でずぶっと刺されるようなのがいくつもある。
「はじめから、空虚なくせに、にやにや笑う。「空虚のふり」」
「苦悩を売り物にするな、と知人よりの書簡あり」
「甘さを軽蔑する事くらい容易なことは無い。
そうして人は、案外、甘さの中に生きている。
他人の甘さを嘲笑しながら、自分の甘さを美徳のように考えたがる。」
全編通して思うのは、実際、君は何をしたのです?
と問われ続けている感じを受ける。
また、逆説的な表現で真意を突いてくるのも自分が太宰 治を好きなところでもある。
「子供の頃に苦労して、それがその人のために
悪い結果になったという例は聞かない。
人間は子供の時から、どうしたって悲しい思いをしなければならぬものだ。」
とかね。
最後の「如是我聞」も痛快。
某作家を徹底的に罵倒し続けている。ここまで言うか〜(笑)というくらい。
ということで、「斜陽」とこの某作家の作品も読みたくなったよ。
2014年9月1日月曜日
古本屋四十年
昭和28年、若干二十歳で下町に古本屋を開業したまさしく古本屋青春奮闘記。
そば屋に入って「ライスカレー」を頼んだり、
ダイハツの軽三輪ミゼットがでてきたりと当時の空気感が満載。
本書全般を通して、やや自虐的ともいえる
働き過ぎな自分を卑下する視点があり
確かに貧しく苦しい生活を続けていくのだが、
古書組合の活動や市の競りを通じて
業界の中でしっかり成長していく姿が綴られている。
面白いのは、やはり古本の「流行り」のところで、
三島由紀夫事件後の関連書籍の急騰や、
デパート催し物会場での初の展示即売会でのマニアの殺到ぶりは想像を絶する。
しかし、今は映画やテレビの興隆、メディアの多様化の中で
希少価値な品物が底をついてきてジリ貧感に苛まれる。
そんな中で、著者は大好きな島崎藤村の肉筆原稿や書簡などを蒐集しながら
古本古書の将来は、一つのキーワードをもって明るいと言っている。
若い人は、もっともっと先をみて商売をしなさいと言うことにつながっていく。
そば屋に入って「ライスカレー」を頼んだり、
ダイハツの軽三輪ミゼットがでてきたりと当時の空気感が満載。
本書全般を通して、やや自虐的ともいえる
働き過ぎな自分を卑下する視点があり
確かに貧しく苦しい生活を続けていくのだが、
古書組合の活動や市の競りを通じて
業界の中でしっかり成長していく姿が綴られている。
面白いのは、やはり古本の「流行り」のところで、
三島由紀夫事件後の関連書籍の急騰や、
デパート催し物会場での初の展示即売会でのマニアの殺到ぶりは想像を絶する。
しかし、今は映画やテレビの興隆、メディアの多様化の中で
希少価値な品物が底をついてきてジリ貧感に苛まれる。
そんな中で、著者は大好きな島崎藤村の肉筆原稿や書簡などを蒐集しながら
古本古書の将来は、一つのキーワードをもって明るいと言っている。
若い人は、もっともっと先をみて商売をしなさいと言うことにつながっていく。
登録:
投稿 (Atom)