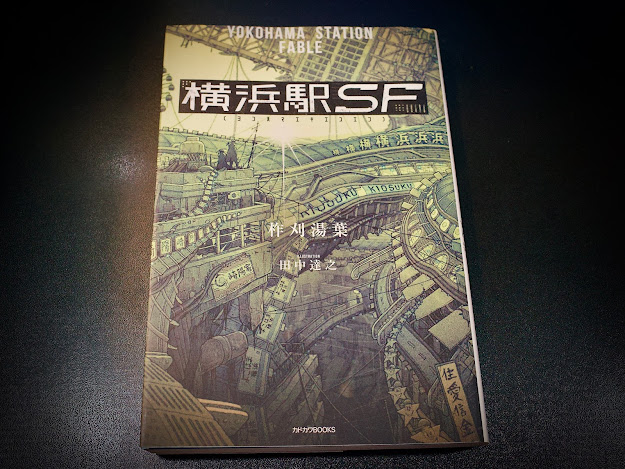読了。
確か、直木賞受賞作だった。
いつも読み始めた後で気づく。
装丁やタイトルからもわかるとおり
ラブホテルの話です。
ところは、北海道、釧路湿原。
七つのお話からなる短編集。
読み始めて、おや?っと思うのは、
最初のお話は、もはや現役ではなくなったホテルローヤル。
すでに廃墟となったホテルローヤルのお話。
そう、七つのお話は時間を遡って語られていきます。
ラブホテルのお話なので、
それなりな男女が出てくるお話ばかりと思いきや
売れないカメラマン、お坊さまとご遺骨、
舅と同居で生活の苦しい中高年夫婦、
ホテル掃除のパートのおばさん、
そして、最後は、ホテルのオーナーが
どういう経緯でホテルを建てるか
ネーミングはどのように決まったのか。
などがつづられていく。
どれもお話が切ないのだ。
ラブホテル自体が、もともと影のイメージがあるところへ
しょっぱなから朽ち果てた廃墟の話から
始まるものだから、余計に登場人物の思いは儚く
男と女の関係も何かやりきれない人生の隅っこを
歩いている感じがする。
ひとりひとりの人間って、必ずしも盤石で強いわけでもなく
ちょっと突っつくとポロっと崩れちゃうような
カゲロウみたいな弱いところがあるんだなと思わせます。
でも、読むと、人に対して優しい気持ちに
きっとなれる一冊だと思います。
どうやら、今年の11月に映画が公開されるみたいですね。
======================
ホテルローヤル
桜木紫乃
集英社 2013年